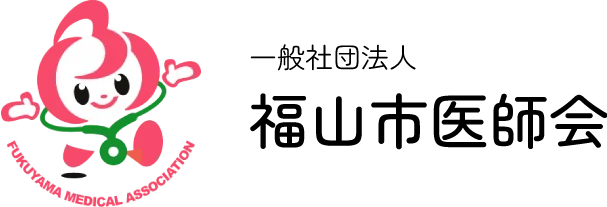2022年12月号
最近の感染症情報
現在、小児の間で流行している感染症を、感染頻度の高い疾患順にお知らせします。

1.感染性胃腸炎 ・・・・・ 増加傾向
2.RSウイルス感染症 ・・ 横ばい
3.ヘルパンギーナ ・・・・ 増加傾向
4.溶連菌感染症 ・・・・・ 減少傾向
5.咽頭結膜熱 ・・・・・・ 横ばい
6.手足口病 ・・・・・・・ 減少傾向
※ 乳幼児の新型コロナワクチン接種が始まりました。
先月から生後6か月から4才までの子ども用の新型コロナワクチン接種が始まりました。
10月から新型コロナウイルスの第8波の流行がはじまり、年末年始にかけて感染者数はさらに増加するおそれがあります。オミクロン株の新型コロナウイルスでは発熱する子どもが多く、熱性けいれんや嘔吐による脱水症状のために入院して治療が必要なことがあります。さらに新型コロナウイルス感染者の急増に伴い、以前は少数であった子どもの重症例や 死亡例も増加しています。特に2才までの子どもと基礎疾患のある子どもが重症化しやすいと報告されています。またお亡くなりになった子どもの半分は5才までの小さな子どもでした。
死亡例も増加しています。特に2才までの子どもと基礎疾患のある子どもが重症化しやすいと報告されています。またお亡くなりになった子どもの半分は5才までの小さな子どもでした。
乳幼児用の新型コロナワクチンは3回の接種が必要で、完了まで約3か月必要になります。持病をお持ちのお子さんも健康なお子さんも早めに新型コロナワクチン接種をうけましょう。まだオミクロン株対応新型コロナワクチン接種をうけていない12才以上のご家族の方も早めに新型コロナワクチン接種をうけましょう。
今月のトピック
妊娠中の食べ物で注意したいこと
食中毒は胎児にも影響することがありますので、予防のために食材は十分に加熱しましょう。寿司やナチュラルチーズ(ピザはOK)にも注意が必要といわれています。一部のビタミンにも注意が必要です。妊娠初期にビタミンAを過剰摂取すると胎児奇形が増加します。注意すべき食材はレバーとうなぎです。レバーは串焼きを週に1本程度までといわれています。どちらも栄養価の高い食材ですが、摂取量に注意しましょう。
魚類はタンパク質豊富ですが、大きい魚は自然界の微量な水銀を取り込んだ小魚をたくさん食べて成長するために水銀を多く含んでいるので、キンメダイやマグロなどは週1回の摂取がお勧めです。海藻に含まれるヨウ素は甲状腺ホルモンの主原料ですが、摂りすぎは胎児の甲状腺機能低下症を誘発します。昆布だしの使用を減らして、魚のだしに変更するとか、みそ汁の具材としてワカメの回数を減らすなどの工夫が必要です。またヒジキには微量のヒ素が含まれているので、煮物小鉢で週に2回までが摂取の目安とされています。
普段は気にせず摂っている食事でも、妊婦さんが摂ったものは胎児の栄養になります。そのため偏食を避けて様々な食材で作られた食事をバランスよく摂るよう心がけましょう。
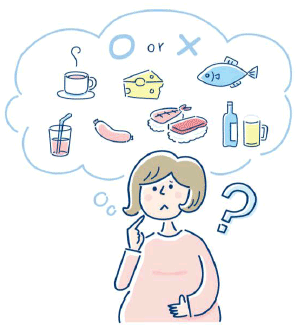
文責:福山市医師会母子保健委員 青江尚志
おくすり一口メモ
目薬の使い方 -福山市薬剤師会-
点眼する前にまず、手を洗いましょう。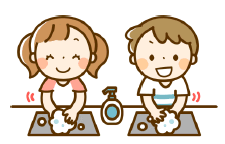 看護、保護の方はもちろんですが、こどもさんも洗いましょう。目薬の違和感でとっさに手が目に行くことが多いからです。小児の場合は「アカンベー」状態で下まぶたのポケットに滴下するのがわりと簡単です。1回に点眼する量は、ほとんどの場合1滴(約50μL)で十分です。これは、まぶたと眼球の隙間に貯められる液量には成人でも限度(約30μL)があって、この限度量以上に点眼してもただ溢れて流れ出てしまうばかりです。多くの目薬は5ML容器ですから、片目使用で100回分。両目で50回分となります。点眼した後はできるだけまばたきをせず、静かにまぶたを閉じ
看護、保護の方はもちろんですが、こどもさんも洗いましょう。目薬の違和感でとっさに手が目に行くことが多いからです。小児の場合は「アカンベー」状態で下まぶたのポケットに滴下するのがわりと簡単です。1回に点眼する量は、ほとんどの場合1滴(約50μL)で十分です。これは、まぶたと眼球の隙間に貯められる液量には成人でも限度(約30μL)があって、この限度量以上に点眼してもただ溢れて流れ出てしまうばかりです。多くの目薬は5ML容器ですから、片目使用で100回分。両目で50回分となります。点眼した後はできるだけまばたきをせず、静かにまぶたを閉じ 1~2分間目をつむったままにしましょう。点眼する際には容器の先端がまぶたやまつげに触れないように注意します。触れることで容器のなかに雑菌が入り繁殖する場合があります。複数の目薬を点眼するときに続けて使うと、先に点眼した液が後の液によって洗い流されてしまうことがあります。はじめの目薬を点眼してから、通常5分位の間隔を空けて次の目薬を点眼しましょう。市販(OTC)の目薬と違って医療用の目薬には「防腐剤」が入っていませんので、開封したなら7日~14日間以上は使用しないでください。
1~2分間目をつむったままにしましょう。点眼する際には容器の先端がまぶたやまつげに触れないように注意します。触れることで容器のなかに雑菌が入り繁殖する場合があります。複数の目薬を点眼するときに続けて使うと、先に点眼した液が後の液によって洗い流されてしまうことがあります。はじめの目薬を点眼してから、通常5分位の間隔を空けて次の目薬を点眼しましょう。市販(OTC)の目薬と違って医療用の目薬には「防腐剤」が入っていませんので、開封したなら7日~14日間以上は使用しないでください。