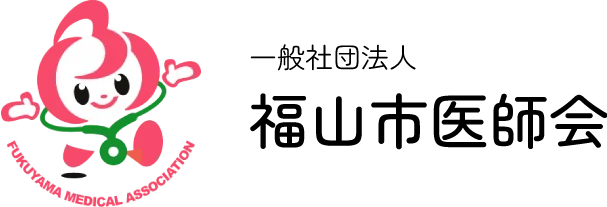【いきいき健康メール】を更新しました(2024年2月号)
- 医療関係のみなさま
- 市民のみなさま
- いきいき健康メール
- 健康コラム
感染症情報
◎地震とTKB
令和6年能登半島地震により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
地震をくぐり抜けた後の健康維持について、テレビ等で対策を呼び掛けているのに気が付かれていると思います。これは災害関連死(震災関連死)と呼ばれている、2次的に命を失うことを減らす目的で行われています。災害関連死の概念は平成7年(1995年)の阪神淡路大震災を機に生まれました。「災害による負傷の悪化、または避難生活等における身体的負担による疾病により死亡する事」を指します。
東日本大震災を例に挙げますと、死者の平均年齢は79.4歳。死因の1位は呼吸器疾患で約31%、このうち86%は肺炎でした。次いで心血管疾患の約27%、脳血管疾患も5%強となっており、低体温症が死因となったかたもいらっしゃいました。熊本地震では、直接の震災の死者の約4倍の災害関連死が生じたと言われています。
災害関連死の予防には医療も必要ですが、インフラの再建までは生活環境を維持する努力はとても重要となります。自宅での生活または避難所生活では、衣・食・住ならぬ寝・食・トイレが重要となります。避難所・避難生活学会などの提言では、TKB(トイレ・キッチンベッド)の整備が重要と有ります。
寝は床での雑魚寝を避けて、就寝環境を整えること(ベッドのように床から30~40cm距離をとることで、ほこり等の吸い込みが減り冷え込みも軽減できます→肺炎予防)。食はバランスの良い特に冬場は温かい食事(最初は届くだけでも有難いと思っていても、おにぎり・パン・弁当が延々続くと栄養バランスも偏り次第に気力が落ちるそうです→体力・免疫力の低下)。意外なところではトイレです。水洗設備が使えない、あるいは順番待ちや便器の汚染でトイレに行きにくくなると水を飲むのを我慢する方もいらっしゃいますが、口の中の洗浄効果を低下させ(→感染症の増加)、また脱水の傾向は血栓を生じやすくなります(→心筋梗塞・エコノミークラス症候群など)。
少々極端な例えとはなりましたが、災害関連死の肺炎と心血管疾患の予防に必要と考えられている対策(心構え)をお届けしてみました。災害は時期も規模も選ぶことはできず、いわゆる防災グッズを頼りにまずは事態を乗り切り、生活を確保しながら健康を維持するしか有りません。改めて皆々様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
文責:福山市医師会 感染症対策委員 浅野 誉久
今月のトピック
◎骨ホルモン
骨について私たちは、「骨格をつかさどる」「カルシウムの貯蔵庫である」「骨髄で血液を産生する」位のことは知っています。しかし骨が色々なホルモンを分泌していることが解ってきました。全身の骨は3~5年で造り替えられると言われています。古い骨が破骨細胞で吸収され、骨芽細胞が新しい骨を造っていきます。その骨芽細胞で『オステオカルシン』や『オステオポンチン』というホルモンが産生されています。『オステオカルシン』には脳に働いて記憶力をアップしたり、筋肉に働いて筋力を増強したり、はたまたテストステロンの分泌を促進し生殖細胞を活性化させたるといった作用があるそうです。また『オステオポンチン』には免疫能を増強させる作用があります。
それでは骨芽細胞を動員させるにはどうしたら良いのでしょう?それには歩いたり、ジョギングしたり、走ったりすることです。それが難しい人は、手を台につけて脚で床を蹴ってジャンプするとか、かかと落しだけでも良いそうです。骨に振動を与えることで骨細胞がセンサーの役割をして骨芽細胞が動員されます。体を動かして骨に刺激を与えることが骨芽細胞を動員させ、骨芽細胞がホルモンを分泌し、若さを保って健康維持につながるそうです。さあ皆さんも健康維持のために骨にどんどん刺激を与えてやりましょう。
文責:福山市医師会 広報委員 高橋 健治
- 休日当番医(地図リンク付き)
http://www.fmed.jp/touban/ - 医療情報ネット
https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2310/initialize?pref=34 - いきいき健康メールバックナンバー
https://www.fmed.jp/cnt/news/genre/ikiiki/