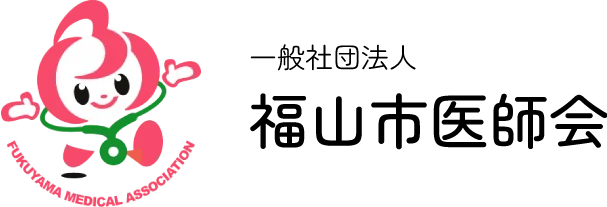【いきいき健康メール】を更新しました(2025年1月号)
- 医療関係のみなさま
- 市民のみなさま
- いきいき健康メール
- 健康コラム
感染症情報
◎歯性上顎洞炎
インフルエンザをはじめ感冒後に続発する上顎洞炎(副鼻腔炎・蓄膿症)はよく知られていますが、歯性感染が上顎洞に波及して起こる歯性上顎洞炎はあまり馴染みがないものの日常診療においては比較的遭遇します。以前は未処置の齲歯(むし歯)が原因とされていましたが、近年は歯内治療(根管治療)後の歯が原因歯になることがほとんどで最近では口腔インプラント治療に伴う歯性上顎洞炎も増加傾向にあります。
片側性が多く症状は一般の上顎洞炎とほぼ同様で通常、歯自体は無症状のことが多いようです。診断は臨床経過より歯性上顎洞炎を疑いCT検査を行います。
治療について耳鼻咽喉科と歯科で統一された見解はなく、歯科においては原因歯の抜歯が基本とされていますが必ずしも根治に至ることはなく、逆に最近、耳鼻咽喉科の間では咀嚼等のQOLを考えて骨植が良く動揺のない原因歯は可能な限り保存し上顎洞炎を治癒することが推奨されてきています。
まず耳鼻咽喉科での鼻処置、ネブライザー等の局所処置、抗生剤投与と歯科での再根管治療による保存的治療を併用して行い改善が得られなければ抜歯せずに内視鏡下鼻内副鼻腔手術(ESS)を行うという流れです。ESSは病的粘膜除去と鼻腔と上顎洞間の換気・排泄の確保を目的とし、術後の原因歯の保存率は高く100%近い報告もみられます。
特に自由診療であるインプラントでは抜去による患者の経済的損失が大きく抜去しても治癒に至らない例もあるためESSでインプラント温存が充分期待できることも考慮すれば、今後は耳鼻咽喉科と歯科とが連携を強め診療することが大事と思われます。
文責:福山市医師会 感染症対策委員 岡本 宏司
今月のトピック
◎アルコールとのつきあい方
12月から1月にかけては、忘年会、新年会、家族や友人との集まりなどがあり、飲酒の機会が多いことでしょう。
「酒は百薬の長」ということわざがありますが、最近の研究では、飲酒しない人よりも少量飲酒する人のほうが健康状態がよいというのは幻想かもしれず、少量であっても害のほうが大きい可能性があるといわれています。
いわゆる「飲める人」「飲めない人」は遺伝子によって規定されており、また性別、年齢によっても影響の大きさに違いがありますが、摂取したアルコール量が多くなればなるほど様々な病気のリスクが高まります。
長期にわたって大量の飲酒を続けたことによりアルコール依存症になると、仕事にも家庭にもさらに大きな問題が生まれ、断酒(一滴も飲まない)が必要になります。
厚生労働省が昨年2月に、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進を図るため、「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001223643.pdf
成人の1日あたりのアルコールの摂取量の目安を、男性で40g未満、女性で20g未満としています。これは、純アルコール換算で、女性でビール中瓶1本(250ml)、日本酒1/2合弱、焼酎(25度)50ml、ワイン1杯(100ml)程度に相当します。
厚生労働省が、純アルコール量とアルコール分解時間を把握するためのWebツールとして「アルコールウォッチ」を公開しています。
https://izonsho.mhlw.go.jp/alcoholwacth/
お手持ちのスマートホンでつかってみてください。
翌日の予定に影響を及ぼさない飲酒量を判断する目安にできますよ。
でもいったん飲んでしまうと、「そんなことはどうでもいい」と思ってしまい、つい量が増えてしまうものです。
日頃から自分の体質や状況について考慮した上で、飲み方の目安を考えておくことをお勧めします。
文責:福山市医師会 広報委員 古庵 路子
- 休日当番医(地図リンク付き)
http://www.fmed.jp/touban/ - 医療情報ネット
https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2310/initialize?pref=34 - いきいき健康メールバックナンバー
https://www.fmed.jp/cnt/news/genre/ikiiki/