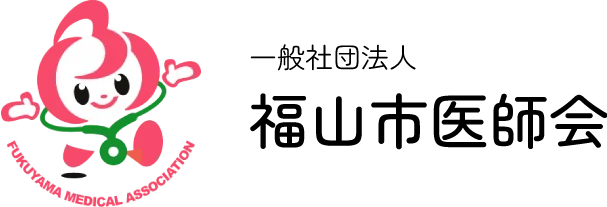いきいき子育て支援情報(2025年2月号)
- 医療関係のみなさま
- 市民のみなさま
- いきいき子育て支援情報

最近の感染症情報
現在、福山市内にて小児の間で流行している感染症を、感染頻度の高い疾患順にお知らせします。
- 感染性胃腸炎 増加傾向
- インフルエンザ 減少傾向
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 増加傾向
- 流行性角結膜炎 減少傾向
- RSウイルス感染症 増加傾向
- 伝染性紅斑 増加傾向
- 突発性発しん 横ばい
続いて、咽頭結膜熱、マイコプラズマ肺炎などが少数報告されています。
*インフルエンザA型とインフルエンザB型
インフルエンザにはA型とB型があることをご存じでしょうか。実はC型もD型もありますが、ふだんの生活の中で重要なのはA型とB型です。
A型はウイルスの構造が変わりやすい特徴があり、鳥インフルエンザのような動物のインフルエンザが人へ感染することもあるため、パンデミック(世界的な流行)の原因になりやすいと言われています。新型インフルエンザという言葉を聞くことがありますが、これはA型で大きな変化が起きて、新たなウイルスとして注目されるときに使われる名前です。
B型は主に人間に感染するウイルスで、A型ほどの大きな流行にはなりにくいですが、症状が長引くことがあります。
インフルエンザになったときの症状について、A型が強く、B型はそこまで強くない、という情報もありますが、実際はA型とB型の間で大きな違いはないとされ、B型にも注意が必要です。流行時期には違いがあり、ふつうの年では先にA型の流行が始まり冬の初めから春先まで流行し、つづいてB型の流行が始まり4~5月になっても残ることがあります。なので、インフルエンザのシーズンが終わったと思って油断していると、B型に感染してしまうことも少なくありません。
福山市では12月末からインフルエンザが流行し、12月16日からインフルエンザ警報が発令されていますが、今流行しているのはA型です。全国の他の地域ではB型が少しずつ出ていると報道されていますが、福山市ではこれから流行が始まるかもしれません。
1月号でもマスク着用や咳エチケットなどインフルエンザを防ぐ心がけをお話しましたが、ひきつづき油断せず過ごしていきましょう。
また、インフルエンザが重症になるのを防ぐにはワクチンが有効で、ワクチンはB型インフルエンザにも効果があります。今シーズンインフルエンザワクチンを受けていない人は、B型の流行に備えるために、ワクチンを受けることを積極的に考えてみてください。
今月のトピック
おちんちんの話
男の子のおちんちんは、皮膚(包皮)に包まれています。おしっこは、おちんちんの先端(包皮口)から出てきます。「包茎」とはおちんちんの先端の包皮口が狭いために包皮をむくことができない状態をいいます。生まれてきた赤ちゃんはみんな「包茎」です。包茎は年齢が上がるにしたがって少なくなり、5歳の時点では約90%の男子が少しはむける状態になります。
包茎のおちんちんをよく見てみると、包皮の下に黄色い脂肪のかたまりのようなものが透けて見えることがあります。これは、あかの一種で「恥垢(ちこう)」といいます。これにより自然と包皮と亀頭表面の分離が進み、むけやすくなります。成長と共に包皮がむけてくると自然に排出されるので特別な処置は必要ありません。
一般的に、こどもの包茎はほとんどが治療を必要としません。医療機関の受診が必要なケースは3つあります。
①おちんちんに赤味や腫れがみられ、触らなくても痛かったり、おしっこのときに痛みを感じる場合。亀頭包皮炎が疑われ、抗生物質をのんだり軟膏を塗って治療します。何度も繰り返す場合は、包茎の治療を考えます。
②おしっこをするときに、包皮の中におしっこがたまって先端がふくらんだり、おしっこが細くしか出ないような場合。
③5歳になっても、全くむけない場合
包茎に対して絶対にやってはいけないのは、包皮を引っ張って無理にむいてしまうことです。亀頭が狭い皮膚で締め付けられて血行障害をきたし、緊急治療が必要となります。
包茎の治療ですが、最近では痛みを伴わない治療(ステロイド外用療法)が主体となってきました。合併症にも配慮が必要であり、小児外科での治療をお勧めします。
こどもの包茎がいわゆる「病気」ではないことを認識して、大人の思惑によって健康なこどもを肉体的・精神的に傷つけることがないように心を配ることが大切です。
文責:福山市医師会 母子保健委員 高橋康太
おくすり一口メモ
子供の抗生物質の使い方と注意事項(その③)~抗生物質の乱用と耐性菌~ -福山市薬剤師会-
抗生物質の誤った服用は、耐性菌の発生を引き起こす大きな原因となります。耐性菌とは、抗生物質が効かなくなった細菌のことで、治療が難しくなり、より強力な薬が必要になったり、場合によっては有効な治療法が限られることもあります。特に子供は免疫機能が未発達なため、耐性菌による感染症にかかると重症化しやすく注意が必要です。
耐性菌を防ぐためには、抗生物質を適切に使うことが重要です。症状が軽快したからといって途中で服用をやめると、細菌が完全に死滅せず、耐性菌が生じるリスクが高まります。医師が指示した服用期間を必ず守りましょう。
また、他人の処方薬を使ったり、以前の処方薬を自己判断で再利用することも厳禁です。風邪やウイルス感染症には抗生物質は効果がないため、自己判断で使用しないようにしましょう。抗生物質は病状や細菌の種類によって適切なものが異なるため、誤った使用は効果がないばかりか、耐性菌を増やす原因になります。
耐性菌で治療の選択肢が減るというリスクを考慮し、正しい服用を心がけましょう。
次回は子供の便秘と下剤の正しい使い方について詳しく解説します。