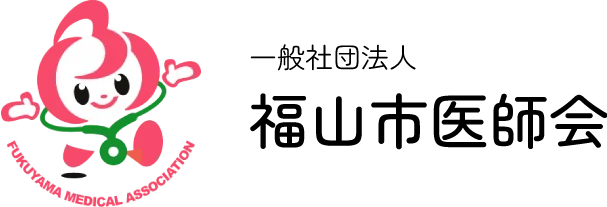いきいき子育て支援情報(2025年3月号)
- 医療関係のみなさま
- 市民のみなさま
- いきいき子育て支援情報

最近の感染症情報
現在、福山市内にて小児の間で流行している感染症を、感染頻度の高い疾患順にお知らせします。
- 感染性胃腸炎 増加傾向
- 新型コロナウイルス感染症 横ばい
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 減少傾向
- インフルエンザ 減少傾向
- RSウイルス感染症 増加傾向
- 流行性角結膜炎 増加傾向
- 突発性発しん 減少傾向
続いて、手足口病、マイコプラズマ肺炎などが少数報告されています。
*RSウイルス感染症について
今年もRSウイルス感染症が増える時期になりました。福山市では1月後半から、徐々に感染者が増え、2月なかば以降で流行期に入ったと思われます。例年流行期のたびに、いろいろな情報を耳にされていると思いますが、いまいちどおさらいをしておきましょう。
RSウイルス感染症は、RSウイルスによる主に呼吸器の感染症です。何度も感染し発症しますが、生後1歳までに半数以上が、2歳までにほぼ100%の小児が感染するとされています。RSウイルスに感染すると、2~8日の潜伏期間を経て発熱、鼻汁などの症状が数日続きます。多くはひどくなることはなく自然になおりますが、咳がひどくなる、ゼイゼイする、呼吸困難となるなどの強い症状が出て、細気管支炎、肺炎へとなる場合があります。また、重篤な合併症として注意すべきものに、無呼吸があり、特に生後1か月未満の新生児に起こることがあります。
感染が重症化するリスクの高い小児として、早産児、また心臓や肺、神経や筋、免疫の異常がある小児に注意が必要です。一方で、慢性的な呼吸器疾患をもつ高齢者も重症肺炎を起こすことがあり、同様に注意が必要です。
RSウイルスは主に接触感染と飛沫感染で感染が広がります。接触感染ではRSウイルスに感染者との接触や、感染者が触れたドアノブ、手すり、スイッチ、机、椅子、おもちゃ、コップ等などを触ったり、なめたりすることで感染します。飛沫感染ではRSウイルスの感染者の咳やくしゃみなどで口から飛び散るしぶきを浴びて吸い込むことにより感染する飛沫感染があります。
接触感染の対策としては、子どもたちが日常的に触れるおもちゃ、手すりなどはこまめにアルコールや塩素系の消毒剤などで消毒し、流水・石鹸による手洗い、手指衛生が重要です。飛沫感染の対策としては、鼻汁、咳などの呼吸器症状がある場合はマスクが着用できる年齢の子どもや大人はマスクを使用することが大切です。
今月のトピック
大人も子供も、朝ごはんを食べましょう
 朝ごはん、食べてますか?
朝ごはん、食べてますか?
小中学生の10-20%が朝ごはんを食べていないという報告もあります。
朝食は1日の始まりに頭や体のパワーの源になるのはもちろんですが、朝食を食べるメリットは他にもたくさんあります。朝食を取る習慣がある人は、食べない人に比べ、学習習慣ができていて学力が高い、早寝早起きで良好な生活リズムを保てる、家族や友人を大切に思い、ストレスやイライラを感じることが少なく、心の状態を良好に保てているとの調査結果もあります。
忙しい朝ですが、少しずつ朝食を取る習慣を作っていきたいですね。①脳のエネルギー源炭水化物(ご飯パン、麺、芋、シリアルなど)、②体温を上げ体を目覚めさせるタンパク質(卵やチーズ、乳製品、肉、納豆や魚)、③体の調子を整えるビタミン、ミネラル(野菜や果物、海藻)から少しずつ組み合わせを意識するといいそうです。
福山市でも、朝食を毎日食べる人を増やそうと、ヘルシーメニューコンテストを毎年開催しています。今年度も福山市内の小中高校生からたくさんの素晴らしいアイデアが寄せられ、入賞作品は福山市のホームページに掲載されています。見た目にもとても美味しそうで手早く作れる料理がたくさん載っていますので一度ぜひご覧になって作ってみてください。
文責:福山市医師会 母子保健委員 奥村 みどり
おくすり一口メモ
子供の便秘と下剤の正しい使い方(その①)~便秘の原因と病院に相談すべきサイン~ -福山市薬剤師会-
子供の便秘にはさまざまな原因があり、一時的なものと注意が必要なものを見極めることが大切です。一般的な原因として、食物繊維や水分の不足、運動不足、排便の我慢、ストレスなどが挙げられます。特に、トイレトレーニング期のプレッシャーや、幼稚園・保育園の環境変化が影響することもあります。また、排便時の痛みが原因で便を我慢してしまい、便秘が悪化するケースも少なくありません。
しかし、次のような症状が見られる場合は、医師に相談が必要です。
・1週間以上排便がない
・便が非常に硬く、排便時に強く痛がる
・血が混じった便が出る
・お腹が異常に張って苦しそう
・食欲がなく、元気がない
これらの症状は、腸閉塞や先天的な病気が原因の可能性もあります。単なる便秘だと思って放置せず、異常を感じたら医師に相談しましょう。
次回は、便秘の改善に使われる下剤の種類と適切な使用方法について解説します。