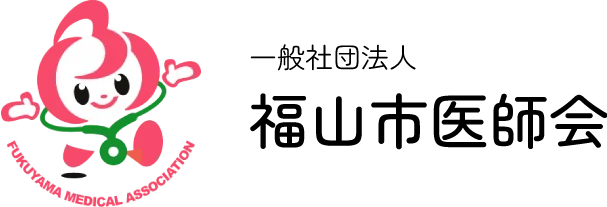【いきいき健康メール】を更新しました(2025年3月号)
- 医療関係のみなさま
- 市民のみなさま
- いきいき健康メール
- 健康コラム
感染症情報
◎ダニからの感染症
ダニからの感染症というと、備後地域においては、日本紅斑熱やSFTSが挙げられますが、日本紅斑熱(昨年505症例)、重症熱性血小板減少症候群〔SFTS〕(同120)、ツツガムシ病(同349)よりさらに稀な感染症も存在しています。
ライム病:日本ではライム病の原因菌を媒介するマダニは、北海道と本州、四国、九州の山間部に生息しており、年間25例報告されています。感染場所としては北海道が殆どで、海外でマダニに刺された後に国内で発症する例も多いです。欧米では年間数万人の感染者がいます。
回帰熱:ボレリア(Borrelia spp.)による感染症であり、ダニやシラミにより媒介されます。古典的回帰熱と、2011年にあらたに発見された回帰熱ボレリアによるBorrelia miyamotoi disease (BMD)が知られています。推定感染地域はほぼ北海道で占められおり、年間11例報告されています。
ダニ媒介性脳炎:ダニ媒介脳炎(Tick-borne encephalitis: TBE)はTBEウイルスの感染によっておこるダニ媒介感染症です。特異的な治療法はなく、高い致命率と重度の障害を残す疾病です。TBEは、世界では欧州(南ドイツや東欧、ロシア等)を中心とした流行がありますが、日本では過去に北海道で7例(うち、2024年に2例)報告されています。
2024年9月13日に「タイコバック水性懸濁筋注」が発売となっており、ダニ媒介性脳炎は現在国内承認ワクチンで予防接種が可能な疾患です。
ダニ媒介感染症は、ダニの刺咬を防ぐことが基本的かつ最善の予防策です。草むら等のダニが多く生息する場所へ立ち入る際は、肌の露出が少ない服装の着用や、適切な忌避剤の使用等の対策が必要です。
文責:福山市医師会 感染症対策委員 眞鍋 明広
今月のトピック
◎骨粗鬆症とは ~予防と治療の大切さ~
骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は、骨の密度が低下し、骨がもろくなる病気です。特に高齢者や閉経後の女性に多く、転倒などの軽い衝撃でも骨折しやすくなります。骨折をすると、寝たきりになるリスクが高まり、生活の質が大きく低下してしまいます。そのため、骨粗鬆症の予防と早期発見がとても大切です。
骨密度測定で早期発見を!
骨粗鬆症は自覚症状がほとんどなく、気づいたときには骨折していることも少なくありません。そこで重要なのが「骨密度測定」です。骨密度は、健康診断や整形外科、内科などで簡単に測定できます。特に50歳以上の方や、家族に骨粗鬆症の人がいる場合は、一度検査を受けることをおすすめします。
治療薬の継続がカギ
骨粗鬆症の治療には、骨を強くする薬が処方されます。しかし、症状が目に見えにくいため、途中で薬をやめてしまう人もいます。治療を途中でやめると、骨折のリスクが高まり、せっかくの予防効果が得られません。医師の指示に従い、根気よく治療を続けることが重要です。
生活習慣を見直そう!
カルシウムやビタミンDを含む食事、適度な運動、日光浴を習慣にすることで、骨の健康を維持できます。普段の生活から骨を大切にし、骨折を防ぎましょう。
文責:福山市医師会 広報委員 高橋 健治
- 休日当番医(地図リンク付き)
http://www.fmed.jp/touban/ - 医療情報ネット
https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2310/initialize?pref=34 - いきいき健康メールバックナンバー
https://www.fmed.jp/cnt/news/genre/ikiiki/