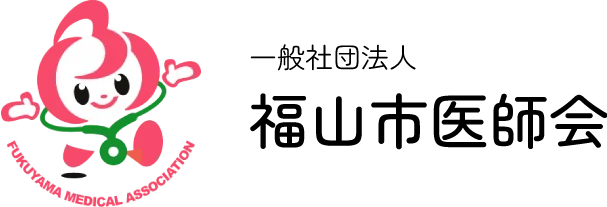いきいき子育て支援情報(2025年4月号)
- 医療関係のみなさま
- 市民のみなさま
- いきいき子育て支援情報

最近の感染症情報
現在、福山市内にて小児の間で流行している感染症を、感染頻度の高い疾患順にお知らせします。
- 感染性胃腸炎 減少傾向
- RSウイルス感染症 減少傾向
- 流行性角結膜炎 減少傾向
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 減少傾向
- インフルエンザ 横ばい
- 新型コロナウイルス感染症 横ばい
- 感染性胃腸炎(ロタウイルス) 減少傾向
続いて、突発性発しん・咽頭結膜熱などが少数報告されています。
*感染性胃腸炎に気を付けましょう
福山市では2月の中旬から感染性胃腸炎の流行が続いています。主な流行時期は秋から冬とされますが、今後もひきつづき注意が必要です。
感染性腸炎はウイルスや細菌などの病原体による感染症です。特に冬に流行するウイルス性胃腸炎の原因となるウイルスにはノロウイルス、ロタウイルスなどがあります。感染者の嘔吐物や便を触った手や、その手でさわったものを介して口に入ったり、汚染された食品や水を口にしたりすることで感染し、ヒトの腸管で増殖して嘔吐や下痢腹痛などを起こします。
ウイルス性胃腸炎の最も基本的な予防方法は手洗いです。調理や食事の前や排便後は石けんと流水で十分に手を洗い、手洗い後は清潔なタオルで手を拭きましょう。また、調理時にはカキなどの二枚貝は中心部まで十分に加熱し、野菜や果物などの生鮮食品は十分に洗浄しましょう。
感染した人の便、吐物には多量のウイルスが含まれるので、取扱は十分に注意して下さい。処理する場合は素手で触れないようにして、マスクや手袋を着けペーパータオル等で拭き取り、付着していた床などの消毒をしましょう。作業後はしっかり手洗いをしましょう。重要な注意点は感染性胃腸炎の主な原因となるウイルスはアルコール消毒の効果が乏しいことです。塩素系の漂白剤で処理しましょう。
感染した場合は特別な治療法はなく、症状に応じた治療となります。乳幼児や高齢者等は重症化する場合があるので、より注意が必要です。
今月のトピック
やけどをしたときの応急処置
熱湯や油、炊飯器からの水蒸気やアイロン、夏は花火、冬はストーブなど意外に多いやけどのリスク、10歳未満の子ども達に圧倒的に多いことが知られています。やけどは適切に対処しなければ、治るのに時間がかかったり痕が残ったりしてしまいます。
先ず大切なことは、やけどの部位を直ぐに冷やすことです。水道水を流しながら少なくとも15~30分程度しっかり冷却することで、症状の進行を抑え痛みを和らげる効果があります。範囲が広ければシャワーで冷やすことも一法です。お湯などが服の上からかかった場合は、無理やり脱ぐと傷害された皮膚が剥がれたり水ぶくれが破れて傷が深くなることがあるため、服の上から流水で冷却すると共に衣服の下に他にもやけどがないか注意深く観察しましょう。
水ぶくれが起こっている場合、中の液体には傷を治す成分が含まれているので破かないほうが有利です。水ぶくれにラップやポリ袋を当てて、その上から流水で冷やすのがお勧めです。
応急処置として患部を充分に冷却したら、やけどの状態を観察し、水疱が生じている場合(II度熱傷)や皮膚が白や褐色に変色している場合(III度熱傷)には、傷害が深い可能性があるため医療機関の受診が必要です。
文責:福山市医師会 母子保健委員 池田政憲
おくすり一口メモ
子供の便秘と下剤の正しい使い方(その②)~下剤の種類と特徴について~ -福山市薬剤師会-
子供の便秘が長引く場合、下剤を使用することがあります。いくつかの種類があり、症状に合わせて使い分けます。
①浸透圧性下剤(糖類のマルトースや塩類の酸化マグネシウムなど)
腸内に水分を引き込み、便を柔らかくする作用があります。習慣性が少なく、小児でも比較的安全に使用可能です。
②刺激性下剤(センナやピコスルファートナトリウムなど)
腸を直接刺激して排便を促しますが、長期使用すると腸が慣れ、効果が弱まることがあります。小児には慎重に処方されます。
③膨張性下剤(食物繊維系)
水分を吸収し、便のかさを増やして排便を促します。水分を多めに摂取するようにしましょう。
④坐薬・浣腸(ビサコジルや炭酸水素ナトリウムなど)
即効性があり、排便が困難なときに使います。頻繁に使用すると自力で排便する力が弱まるため、緊急時のみが望ましいです。
下剤を使用する際は、医師の指示に従い、正しい用法・用量を守ることが大切です。
普段から便秘にならないよう、次回は便秘を予防する生活習慣について解説します。