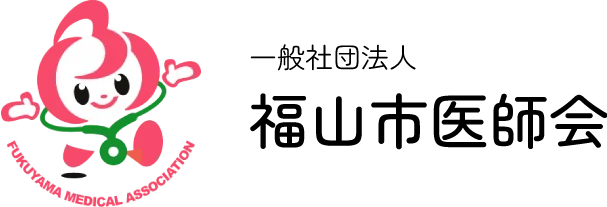いきいき子育て支援情報(2025年8月号)
- 医療関係のみなさま
- 市民のみなさま
- いきいき子育て支援情報

最近の感染症情報
現在、福山市内にて小児の間で流行している感染症を、感染頻度の高い疾患順にお知らせします。
- 急性呼吸器感染症 横ばい
- 感染性胃腸炎 減少傾向
- ヘルパンギーナ 横ばい
- A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 減少傾向
- 流行性角結膜炎 横ばい
- 新型コロナウイルス感染症 横ばい
- 突発性発しん 横ばい
続いて、RSウイルス感染症、伝染性紅斑 などが少数報告されています。
*ヒトパレコウイルスをご存じですか?

近年、夏場にみられる感染症のひとつにヒトパレコウイルス感染症があります。2004年に初めて知られることになった、新しい感染症の一つです。
新生児や乳児期早期にこの感染症(特にヒトパレコウイルス3型)にかかると、発熱、頻脈、網状チアノーゼ(皮膚が網目状になり青紫色状に変化する)、発疹や手のひらや足の裏に紅斑など出ることがあります。重症な場合は無呼吸を起こしたり、脳炎、髄膜炎になったりして命に危険が及ぶこともあります。一方で、大人がかかっても夏かぜとあまり変わらない症状なので、気が付かないことが多いので、注意が必要です。
ヒトパレコウイルスは夏かぜの代表である手足口病やヘルパンギーナの原因であるエンテロウイルスの近縁種であり、夏かぜと同じように手洗い、うがいが有効です。家族間のタオルや食器の共有も避けるようにしましょう。新生児がいるご家庭では特に気を付けるようにしましょう。
文責:福山市医師会 理事 荒木 徹
今月のトピック
赤ちゃんの睡眠について

生後すぐの赤ちゃんは体内時計がうまく機能していませんので、地球の時間に合わせた自然な覚醒睡眠のリズムがまだ整っていません。人はレム睡眠(浅い眠り)とノンレム睡眠(深い眠り)を繰り返しています。生まれてすぐの赤ちゃんは、レム睡眠(浅い眠り)が多いため、すぐに起きてしまいます。睡眠覚醒リズムは生後7週頃から形成され始め、生後11週までに8割の赤ちゃんが睡眠覚醒リズムを獲得すると言われています。その結果、生後3か月頃から昼間起きていることが多くなり、昼夜の区別がつくようになってきます。この覚醒睡眠リズムを獲得するためには、光と音が大切とされています。朝の光を浴びることと、夜間の授乳時に間接照明を使用することも大事です。また、日中の炊事や洗濯などの生活音も覚醒睡眠のリズムの獲得には重要です。赤ちゃんの覚醒睡眠リズムは、両親の睡眠に影響を及ぼします。赤ちゃんが覚醒睡眠リズムを獲得すると両親の睡眠状況は改善し、睡眠不足が解消されてきます。赤ちゃんの睡眠について知っていれば、赤ちゃんが寝てくれない時の対応に役立つかもしれません。
文責:福山市医師会 学校保健委員 安井雅人
おくすり一口メモ
小児用ビタミン剤の選び方と注意点(その③)~ビタミン剤の選び方と注意事項~ -福山市薬剤師会-
小児用ビタミン剤を選ぶ際は、まずは食事で十分に栄養が摂れているかを見直すことが大切です。普段の食事で必要量を満たせている場合、サプリメントを無理に追加する必要はありません。
どうしても不足が心配なときは、子どもの年齢や体重に合った用量であること、過剰摂取の心配がないことを確認しましょう。特に肝油ドロップなどに多く含まれるビタミンAやDなどの脂溶性ビタミンは体に蓄積されやすく、摂り過ぎると頭痛や吐き気などの副作用を起こすことがあります。カルシウム剤にもビタミンDが含まれるものがあるため、成分を確認してみましょう。
「お菓子感覚でつい食べ過ぎてしまう」ということも起こりやすいため、子どもの手の届かない場所で保管し、大人が管理することが重要です。
また、健康食品やサプリメントだけに頼り過ぎず、あくまで食事の補助として利用することを心がけましょう。体調不良や発育が心配な場合は医師や薬剤師に相談し、必要に応じて適切な製品を選ぶようにしましょう。無理なく、賢く活用することが子どもの健康を守るポイントです。