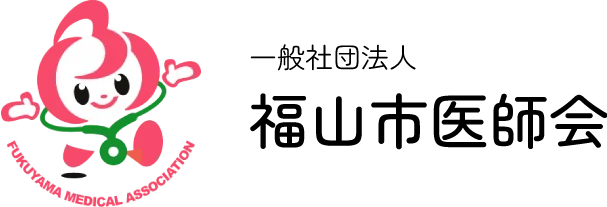【いきいき健康メール】を更新しました(2025年9月号)
- 医療関係のみなさま
- 市民のみなさま
- いきいき健康メール
- 健康コラム
感染症情報
◎まだまだ暑い!食中毒のはなし(つづき)

9月になったのに秋の気配はどこへやら...夏にも冬にも問題となる食中毒のはなしを、先月につづきお届けします。
細菌が原因となる食中毒は夏場(6月から8月)に多く発生しています。その原因となる細菌の代表的なものは、腸管出血性大腸菌(O157、O111など)やカンピロバクター、サルモネラ属菌などです。食中毒を引き起こす細菌の多くは、室温(約20℃)で活発に増殖し始め、人間や動物の体温ぐらいの温度で増殖のスピードが最も速くなります。例えば、O157やO111などの場合は、7℃から8℃ぐらいから増殖し始め、35℃から40℃で最も増殖が活発になります。また、細菌の多くは湿気を好むため、気温が高くなり始め、湿度も高くなる梅雨時には、細菌による食中毒が増えます。
一方、ウイルスが原因となる食中毒は冬場(11月から3月)に多く発生しています。食中毒の原因となる代表的なウイルスであるノロウイルスは、調理者から食品を介して感染する場合が多く、ほかに二枚貝に潜んでいることもあります。ノロウイルスによる食中毒は、大規模化することが多く、年間の食中毒患者数の4割以上を占めています。
ほかにも、毒キノコやフグなどの「自然毒」、近年発生の多いアニサキスなどの「寄生虫」なども、食中毒の原因となっています。
このようにさまざまな原因物質によって、食中毒は1年中発生しています。
暑いとはいえ、「食欲の秋」「秋の味覚」など、秋は食べ物の楽しい季節。だからこそ感染性胃腸炎には十分注意したいものです。
文責:福山市医師会 感染症対策委員 小山 祐介
今月のトピック
◎ダイエットと体重測定について

自宅でできる体調管理の手段として、体重測定は有用です。できれば毎日測定されることをお勧めします。
毎日体重を測ってみると結構変動が大きくて、1日の中でも1kg以上増えたり減ったりしています。食事、排泄、発汗、時間帯にも影響があり、前回の体重との比較だけで肥えたか痩せたかは判断できません。
過体重の方にはダイエットが勧められますが、贅肉、つまり余分についた脂肪を落とすことを目標にしています。エネルギーの蓄えが余っていると考えて、食べ過ぎにならないようにして、消費できるよう体を動かすことがダイエットの基本になるかと思います。短期間で脂肪を何kgも落とそうとして食事のバランスが崩れるのは健康的とはいえません。
毎日10gの脂肪を落としていけば1か月で300g、1年間で3.65kgの脂肪が減ることになりますが、今日の食事運動療法で脂肪が10g減ったかどうかは体重計に乗ってもわかりません。それでも毎日同じような時間に体重計に乗り、増えたり減ったりする中で、以前より大きい数字を見ることが度々あれば原因を考えることが大切ではないかと思います。
文責:福山市医師会 広報委員 阿嶋 猛嘉